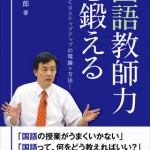Posted By taga on 2015年12月22日
19日のセミナー
なんだか知り合いがけっこういて、
アウェイ感がなかった。
中でも、去年まで4年間指導に行っていた伊丹の学校から
若い先生が3人来てくれていたのはうれしかった。
3月まで行っていたのに、
とっても懐かし感があった。
どこの学校へ行っても、
人とつながりができる。
そのときそのときにいつも自分の全力でありたいなと思っている。
「誠実ってなんですか」
と、最近たずねられたとき
すっと出てきた言葉は
「相手の気持ちになって考えること」
だったが、
今の僕の「誠実」は、そういうことなんだろうなあ。
Category: 心・命の教育 |
19日の会に思ったこと はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月21日
SNS上では、ときどき直接的間接的に管理職への文句が書かれる。
確かに、ひどい管理職もいらっしゃる。
そういう話は目立ってしまう。
そして、良い管理職に恵まれていたら、
ネット上でそれを書き込むことは少ない。
第一、若手にはそれがどれほどありがたいことかを理解できない。
僕を呼ぶ学校の管理職は、優れた方が多い。
おべんちゃらではない。
それは、僕のような人間を学校で活かそうと考える時点で
そうなのだと思う。
視野狭窄だとか「オレのいう事を聞け」的な管理職なら
僕を呼ぶことはしない。
(僕を呼ぶから立派だと言っているのではない。)
年間に五十人近くの管理職とじっくり話す機会がある。
管理職ならではの悩みもあり、
批判をあえて受けている方もいらっしゃる。
なんでもそうだが、
どのくらいの割合で善し悪しなのかを考えないと
いけないよね。
Category: 教師へのメッセージ |
良い管理職の存在 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月20日
あとがきから
国語の授業についての現場の悩みや疑問に答えることを中心にこの本を書き上げました。この執筆は同時に自分の国語教育の中まとめに大きく役立ったように感じています。
年間を通して、全国の学校でいろいろな先生方の授業をたくさん参観する立場にあって、あまりにも国語の授業ができていなくて、頭の痛くなることがあります。若い先生だからではありません。若い先生方は素直で自分が何も判っていないことを自覚しているので、アドバイスもよく聞いてくれます。
ベテラン、中堅の先生方の国語の授業で、つまらない授業、力をつけない授業がよく見かけられるのです。(こんなこと書くと、次から僕の指導に行く学校では若手しか授業をしなくなるかも知れませんが。)
・ただ意味もなく範読する。
・漢字しか教えることはないと思っている。
・文章を解説する講義式になっている。
・教師自身の言葉の使い方がなっていない。
・指導書の赤本を片手に授業をしている。
・言葉が増えていかない。
・本質的な国語の楽しさを伝えられない。
そんな授業を繰り返していては、子どもたちの国語力は伸びていきません。
国語は確かに曖昧な感じのする教科ですが、確実に力をつける方法はあるのです。未来の子どもたちのためにも、「国語の教師力」をアップさせてほしいと思うのです。
この本は、その理論と指針と方法とを示せたのではないかと考えています。
僕の国語教育のもっとも良き理解者である明治図書の林知里さんには、今回も僕の自由に書かせて頂きました。心から感謝致します。
Category: 国語教育, 本の話 |
新著『国語教師力を鍛える―授業づくりステップアップの理論×方法―』 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月19日
支援を要する子どもがいる。
支援の先生と担任が一緒に授業の計画を立て
その授業に応じたその子だけの手立てを打つ。
担任もそこを理解する。
その相互の作業で成り立つ。
先生間のコミュニケーションなしでは、その子はそこにいられない。
この前の公開研のときに「その子」が自然とそこにいられたこと。
同じ学習をこなしたこと。
当たり前なのだけれど、大事なこと。
今回は、特にそれを学ばせてもらった。
体育館での授業という特殊な状況に弱い子どもに対して
前もって、体育館での状況を写真と図でよく理解させていたそうだ。
式典とか、いつもと違うことに対しては
常にそうされているという。
特別支援の視点からすれば当たり前のことかも知れない。
だが、僕は感動する。
並大抵の努力ではない。
自分を抑え、あくまで「その子」のことを考えることに徹底している。
それでいて、授業では、裏方の立場を崩さない。
こういう方の努力が、その子を教室に居続けさせられる。
居続ける必要がなぜあるのか?という問いはあるべきだ。
でも、僕ははっきりしている。
「その子」が発表する姿をクラスの子どもたちがじいっと聴き入っている。
こんな姿は、「その子」を教室から取り出したのでは、かなわない。
そこにその子の「居場所」が存在するということだ。
Category: 社会問題・教育問題 |
特別支援の視点 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月16日
東大阪の小学校での公開研究会。
多くの先生方や委員会のみなさんが集まって盛会だった。
2年生の授業、良かったなあ。
先週アドバイスはしたけれど、一部だけ取り入れて
しかもそれを子どもたちに合わせて、ご自分で考えて授業におとしていた。
8年目の先生。
それは、自分のクラスの子どもたちを熟知しているからできること。
僕がこの授業をしろと言われても絶対にできない。
それは、先生と子どもたちの関係性からしかできないものだから。
「話す・聞く」というテーマの授業は、一ヶ月やそこらがんばってもできない。
一学期にこの2年生立ちを相手に投げ込み授業したから、僕にはよく分かるが
この半年で、子どもたちを育て上げている。
授業は子ども理解の上でしか成り立たないということを
改めて教えてくれた。
先生が笑顔。
子どもたちも笑顔。
そして、授業へののめり込み方。
すごかった。分かる人には、そのすごさが分かる。
子どもたちはこの緊張した中で集中して頭を使った。
こういうとき、子どもたちはぐんっと成長するものだ。
Category: 国語教育, 国語教育 |
いいもの見たなあ はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月15日
巷には不安商品が満ち溢れている。
ボールド、レノアハピネス、消臭力、リセッシュ、・・・。
臭いに対する不安があるから、売れる。
ものにはにおいがあって当たり前だったころには、
絶対に売れなかった商品。
アフラック、Eデザイン損保、・・・。
保険が売れるのは先々に不安があるから。
社会保障がしっかりしていたら、売れない商品。
香酢、芳醇、等の健康食品。
健康に不安があるから、売れる商品。
長寿村では健康食品は売れない。
世の中に不安が蔓延していることの証拠。
その社会の空気を受けて、
子ども達にも不安が広がっている。
漠然とした不安。
敏感な子どもはそこを感じてしまうような気がする。
Category: 社会問題・教育問題 |
不安商品 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月10日
昨日は、中堅の先生の研究授業。
読み込んで読み込んで、
それがよく分かる授業だった。
優れた点はたくさんあったが
「そんなこと僕に聞きたくないでしょ。」
と言って、けっこう厳しい指摘をしたと思う。
彼は、それを「はいはい」とは聞かずに
ちゃんと自分なりの考察が入っている。
それでなくっちゃあ。
はいはいとうかがうだけなんて、つまらない。
最後に、グループ毎に立って話し合ったんだけど
僕は、全員の顔の表情を観察した。
これは凄い。
みんな、学習に向かっている表情。
実はここまでの学習集団にするまでは大変な学年だったらしいが、
ここまで育てたら、後は、どこで子どもたちに任せるかだなあ。
ちょっとうらやましかった。
Category: 国語教育, 学級教育 |
子どもの育ちと国語の授業 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月8日
明日は尼崎の公立校の研究授業。
僕はできるだけ、指摘をせずに
本時の授業レイアウトのための秘伝を伝えた。
長い指導案。
校内研はそれでいい。
みんな読むべきなのだ。
たとえうまくいかないことがあっても、
それは失敗ではない。
なぜなら、研究しているのだから。
一方、次週の東大阪の公開研の場合は
学校を代表しての授業。
だから、事前研のために、足を運ぶ。
アドバイサーというのは、そういうときにこそ必要だと思っている。
指導案だけ見ていても授業が見えてこない。
だからこそ、話し合わないと。
納得の行く授業の流ができたら、
後は、担任と子どもたちの時間。
授業とは、どこまでいっても、そういうものだ。
Category: 国語教育, 国語教育 |
研究授業と公開授業 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月6日
今年は教え子の訃報が多い。
また、一人。
69回生の鹿子木。
病気は仕方ないが、なんとも寂しい。
3年生から6年生まで4年間担任。
この前、僕の還暦祝いのときに
「鹿子木、どうしてんのかな」
という声が上がったのは、何かの予感か。
賢く、リーダーでもあった。
繊細で、公平で、真っ直ぐだった。
いろんなことを考えすぎるくらいに考える男だったが
彼は、その後の人生を悩み考えて
42年間を彼らしく生きたのだろうか。
教え子たちには、「らしく」生きてほしい。
そして、みんな、僕よりも先に逝くな。
絶対に逝くな。
Category: 未分類 |
逝くな はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2015年12月6日
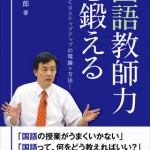
『国語教師力を鍛える
―授業づくりステップアップの理論×方法―』
国語の授業をステップアップしたい先生のために書きました。
第1章 場づくりから考える国語学習
―言語活動とアクティブ・ラーニング―
1 言語活動をどう考えるのか
2 国語科に求められる協同的学習
3 協同学習成立に必要なこと
①目的の明確化/②場の設定/③時間の設定
④まず自分の考えをまとめる/⑤聞き合うルール
⑥適切な教師の立ち位置/⑦聞き合える土壌/⑧個々の観察
4 アクティブ・ラーニング時代にも求められる一斉指導とは
5 「伝統的な言語文化」は体感で教える
(1)小学校で古文漢文の入ってくる意義とは
(2)「親しむ」とは、どうすることか
6 国語学力を高めるために
(1)言語感覚を育てる
(2)言語感覚チェック
(3)言語姿勢が個を育てる
Q1 学びにくい子どもへの対応は?
Q2 音読は、感情をこめるべき?淡々と読むべき?
第2章 国語教師力をアップする(もしくは高める) 文学教材 指導のポイント
1 ステップアップのために意識する3つの観点
(1)国語の力をつけること
(2)情景描写を読み取ること
(3)精神的なレディネスを踏まえること
2 イメージを大切にする
(1)言葉にはイメージがあることを教える
(2)イメージの授業の実際
3 人物設定の視点から見る―教材「ごんぎつね」を例に―
Q3 子どもの生活圏にない言葉は、どう指導するの?
第3章 国語教師力をアップする(もしくは高める) 説明文教材 指導のポイント
1 ステップアップのために意識する3つの観点
(1)指導目標を具体化すること
(2)説明文を読む目的を明確にすること
(3)初読以上の深まりを感じさせること
2 説明文でこそ国語力をつける
(1)読む力は音読と非連続型テキストでつける
(2)まとめる力は指針を示して
(3)書く力は短作文づくりで鍛える
Q4 説明文と物語文の音読は、違うの?
Q5 なぜ、書写するべきなの?
第4章 国語通信で家庭と授業をつなぐ
1 なぜ国語通信を出すのか
(1)家庭での誤った指導を是正する
(2)子どもの作品を載せることで意欲を高める
2 実例で見る国語通信
(1)授業内容を伝える
(2)国語テストの分析・解説
(3)本の紹介
(4)国語のコラムを入れる
(5)学習や宿題のポイントを示す
(6)子どもを認め、励ます
Q6 じっと鉛筆を持ったまま書けない子どもはどうしたらいい?
第6章 スキルアップするための国語科ヒドゥンカリキュラム
(1)文章を読む習慣を持つ
(2)まとまった文章を書く機会をつくる
(3)辞典を手元に置く
(4)言語感覚を磨く
(5)語彙を豊かにする
(6)子どもから聞き切る力を持つ
(7)プレゼン(説明)を練習する
(8)コミュニケーション能力を高める
(9)発声力・朗読力を磨く
(10)ユーモアを鍛える
Category: 国語教育, 国語教育 |
まもなく刊行です はコメントを受け付けていません
タグ: