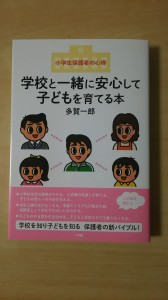Posted By taga on 2016年3月4日
ときどき問い合わせがあるので、
ここでお断りしておく。
4月3日の教師塾は、定員オーバーで
これ以上は引き受けられない。
僕のうちにスペースがないから。笑笑
参加者は、ラフなスタイルでくること。
スカート、スーツは止めた方がいい。
ジャージでもいいが、うちはこの時期、肌寒いときがあるので
その準備もしてくること。
10時ちょうどには、簡単な講座をしたいので、できるだけ、その前にうちに着くようにしてほしい。
ほぼ同学年やTT等のチームで学ぶが、
基本的には一人で僕と相談しながら作っていく。
どんな学年にしたいとか
こういうことを教科の柱にしたいとか
ノートでもメモでもいいから、用意してくること。
厳しく指導するのでそのつもりで。
近くに自販機があるので
気分転換に飲み物を買いに行くこともできる。
食事の時間は短縮したいので、おにぎりやカレーになる。
お菓子たべながらでもオーケー。
うちには、資料は山ほどある。
なんでもあるから、自由に使えるし
自分で買うための絵本を選ぶこともできる。
Category: 講座・研究会の案内 |
教師塾 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年3月2日
6月11日【土】に神戸で国語のセミナーをします。
堀・多賀の恒例の会ですが、
これからは、僕たちが話すだけの会にはしないようにしたいと
思っています。
名古屋でのように、登壇ではなく、提案として
国語の模擬授業をしてくれる先生、歓迎です。
僕と堀さんで解説・アドバイスします。
基本、20分間です。
ふだんの授業の導入部分でもかまいませんし、
投げ込みでもかまいません。
自分では解説せず、参加者を子どもに見立てての
模擬授業です。
ネタはなしです。
希望があれば僕に連絡を下さい。
Category: 未分類 |
公募。拡散希望。 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月29日
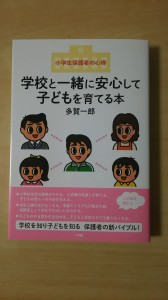
自分の本の出るのがこれだけ楽しみだというのは、
久しぶりの感覚。
作っているうちに、
必要な本だなと思ってきた。
学校や先生を非難する本。
あそこがよくない。
こういうことをなんとかするべきだ。
そういう本が売れる。
親は、ここを直すべきだ。
こんな親のやり方が良くない。
そんな本も並ぶ。
そして、自己啓発本の全盛時代。
もう少し別の視点で考えようよ、
ということを提示できたと思う。
初めての一般書。
良かったら、手にとって下さい。
Category: 本のあるくらし, 本の話 |
『学校と一緒に安心して子どもを育てる本』 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月28日
アクティブラーニングと協同学習について、いろいろなところで取り上げられています。元々は大学と高校の導入だったのですが、中学、小学校でも、触れずに進めるわけにはいかない流になってきました。では、アクティブラーニングとは何なのだろうか。これまでの協同学習と違うのか。丸一日、徹底的に考えるセミナーです。仙台から若手のAL実践家の鈴木優太・尾形英亮両先生を招き、「スクールカースト」などの著作で有名な北海道の中学教師、堀裕嗣と多賀一郎で、二人の実践提案をベースに語ります。徹底的に追究する場になることでしょう。
■ 日時 2016年3月27日【日】 9時半~16時45分
■ 場所 兵庫私学会館 101号室
■ 参加費用 4000円 (26日と両日参加は2000円)
■ 参加人数 50人
■ 内容 9時半開会
① 9時30分~10時 アクティブラーニングに必要なこと 多賀一郎
② 10時10分~11時 鈴木優太からの提案
③ 11時10分~11時25分 フロアでアクティブ
④ 11時25分~11時35分 シェア
⑤ 11時35分~12時 優太の提案を斬る(シェアを受けて多賀が解説、質問)
昼食休憩
⑤ 1時10分~2時 アクティブラーニングの効用と限界 堀裕嗣
⑥ 2時10分~3時 尾形英亮からの提案
⑦ 3時10分~3時25分 フロアでアクティブ
⑧ 3時25分~3時35分 シェア
⑨ 3時35分~4時 尾形の提案を斬る(シェアを受けて堀が解説、質問)
⑩ 4時10分~フロアの質問もまじえての鼎談 鈴木・尾形・堀 コーディネイト 多賀
申し込みは下記サイトから
http://kokucheese.com/event/index/353350/
Category: 未分類 |
徹底的にアクティブラーニング はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月25日
僕は今でこそ教室の「あの子」について各地で語っているが
実際には、真剣に取り組んでいたわけではない。
私学ということもあって、
僕はあまり強い関心はなかった。
ときどき公立で指導していたから、
全然知らないというわけではなかったけれども。
だから、いつも、
「僕には偉そうに語るものはないんですよ。」
という前提でお話させて頂いている。
一度現場を離れて動き出した時に、
これまで自分の周りにもたくさんの「あの子」たちがいたということを
知らしめされた。
ある日、発達障碍のセミナーに参加した時に
会場前のフロアで本を売っている保護者に出会った。
それが「ライト・イット・アップ・ブルー」を日本で広めている
佐伯さんだった。
娘さんが僕の教え子であるが、
僕はこのときまで、この方の息子さんが発達障碍だということを
全く知らなかった。
保護者からはいろいろな話を聞くタイプの僕なのに、である。
その後、自分の周りにたくさん、
発達障碍に悩む保護者の方がいらっしゃることが分かってきた。
これまでもそうだったはずなのに、
なぜ突然のように、そのことが分かってきたのか。
僕自身の目が開き、そこを見るようになったこと。
耳を立て、そういう情報に敏感になったこと。
心を広くして、そういう方の思いを入れられるようになったこと。
等が理由だろう。
つまり、僕自身の問題だったわけである。
目を開き、耳を立てよう。
そうすれば自ずから、声なき声も入ってくるものだ。
「どうして言ってくれないんだろう」
と思う前に、言ってもらえない自分を自覚するべきなのではないか。
Category: 未分類 |
目を開き、耳を立てる はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月24日
新年度から、道徳が教科化して
きっちりと35時間確保が求められる。
2020年度に向けて、英語の教科化と時数が増える。
アクティブ・ラーニングについても考えていかねばならない。
しかも、インクルーシブ教育は、法律を背景として
より高い次元を求められる。
全て正しいことだが
問題は何一つ減らさないことにある。
これまでやってきた「いいこと」は全て踏襲する。
夏休みと業間を減らして少し時間を作るという発想もでてきている。
どんどん息苦しい現場になるだろう。
何がやりたいのだろう。
子どもだって遊ぶ余裕が必要なのに、
それも奪っていく。
減らすことは勇気が要る。
でも、減らさないと、きっとパンクする。
Category: 社会問題・教育問題 |
減らすことを考えろ はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月23日
昨日は青山新吾さんに三宮まで来て頂いて
じっくりと呑んで語る。
4月から施行される法律について、
現場での自覚がないという話になった。
障碍のある子ども、【発達障碍も同じ】への「合理的な配慮」がなければ、
おそらく訴訟という事案が出てくるだろうとも。
それは、当たり前のことを当たり前にしろということであって
それほど生産的な話ではない。
「びしっと怒鳴りつけて静かにさせろ」
というような非合理的なことが許されなくなるだけ。
みんな罰則がついた法律だとわかっているのかなあ。
障碍を持つ子どもの保護者は知ってるよ。
合理的な配慮は、当たり前のこと。
それが現場ではまだ、なかなか染み渡っていない。
でも、法律が何かを解決するわけではない。
暴れる子どもに対して、萎縮したのでは、教育は滞る。
どうしたらいいのかという「合理的なてだて」が必要になる。
インクルーシブ教育というのは、視野を広げた考え方で
障碍のある子どもたちも同じクラスに入れるという発想ではなく
みんなゼロベースでお互いの幸せを考えようということではないか。
僕が「智恵を出し合おう」というのは、そういうことだ。
本気で考えなくてはならない時が来ているということだ。
Category: 社会問題・教育問題 |
教室の「あの子」を語る はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月19日
井上真偽の
とってもめんどうな本。
表紙の軟弱さに騙されてはいけない。
真偽値。充足問題。推論規則。形式的証明。
対偶。実質含意のパラドックス。自然演繹。・・・
こんな言葉は、40年前の田口先生の「論理学」の講義以来である。
これが、アラサー美女の推理小説なんだから、
おそれいる。
僕は途中の論理証明をすっ飛ばしながら読み切った。
この本をおもしろがれるのは、
僕の知っている範囲では、堀裕嗣ぐらいしかいないな、きっと。
Category: 本のあるくらし, 本の話 |
『恋と禁忌の述語論理』 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月18日
教育には、常にミクロの視点とマクロの視点が存在する。
教室で日々起きていることは、
ミクロの視点で解決していくものだ。
一報、教育行政や根本的な教育哲学の在り方というものは、
マクロの視点で語られねばならない。
具体的には、
英語の授業をとりあえずどうするかというのがミクロ。
英語教育というものの在り方をグローバルな視点でとらえるのが、マクロ。
子どもに読み聞かせするのがミクロ。
読書教育について考えるのがマクロ。
というようなこと。
インクルーシブ教育も同じ。
教員の認識改革や教育システムの抜本的な改変などがマクロ。
目の前の暴れる子どもをどうしたらいいか考えるのがミクロ。
現場の教師は、マクロの視点を持ちつつも、
現場で起きていることへの対応を迫られる。
「なんとかしなければ、いけない」のだ。
Category: 社会問題・教育問題 |
ミクロとマクロ はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年2月17日
教室の「あの子」で最も問題になるのが、
はっきり言って、暴れる子どもである。
他の発達障碍は、とりあえず回りの子どもたちに何かつらいことが起きるわけではないから
じっくり取り組めるし、
周囲の理解を進めていくこともできる。
でも、暴力的に出られたり、
学びを邪魔されたりすると、
他の保護者も黙ってはいられなくなる。
教師が「長い目で見てあげてください」と言っても、そうはいかない。
というか、その言葉は使ってはいけない。
被害者に加害者の気持ちを押しつけることになるからだ。
受け入れられるはずがない。
「あの子」の親の思いは、本当に辛いものだろうと思う、想像しかできないが。
「あの親は、なかなか認めようとしない。」
という言葉を聞くと、僕は辛い。
その親の心の奥にどのような思いがあるのだろうか。
それをもっと想像するべきではないだろうか。
でも、そう言う学校側の思いも分からないではない。
先生だって、その子のことを真剣に思っている。
誰も責める気にはならない。
単なる感傷ではなくて、良い智恵はないものだろうか。
Category: こどもの話, 学級教育 |
2 Comments »
タグ: