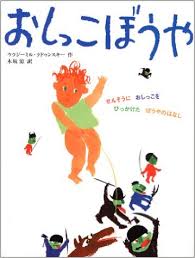Posted By taga on 2016年4月6日
追手門も4年目。
昨年度までの反省もあり、
校長に頼んで昨日、新人たちと話をする。
初日から
大きく出遅れないように。
学級スタートのノートを渡して、話をする。
ともかく、できるだけ最初の授業を観せて欲しいと
スタートの授業から観ることになった。
この子達が、追手門を支えていくのだという使命感が僕にはある。
人が育つには、自己責任がある。
自分しか自分は育てられないのだ。
しかし、土壌を一緒に作ってあげることはできる。
失敗もあり。
若手には失敗する権利があるのだ。
僕は叱責はしない。
指導といいながら、アドバイサーでありたい。
メンターとして「そこにいる」と言うことは
じっくりと観ていけるということでもある。
4年目になり、ようやく僕の教師教育のスタイルが出せるようになった気がする。
追手門に赴任したとき、校長から
「多賀先生、じっくりとやってください。」
と言われたことの意味がようやく分かってきたかな。
Category: 教師へのメッセージ |
うちの新人 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月4日
『教師の言葉でクラスづくり クラスを育てるいいお話』の姉妹版。
上の本は、クラス全体に投げ掛ける言葉集。
こちらは、子ども個人や小集団に使う言葉集。
いい言葉だと思っても、なかなか使えないもの。
どのタイミングで使えば良いかのヒントが満載。
ここというときに失敗しないために、
言葉の使い方を考えよう。
全国の教育をリードする教師達の
「こんな言葉をこんなときに掛けると効果的」
という実践が並んでいる。
2冊セットで安くなるというわけにはいかないけれど
僕のセミナーでは、セット料金にするつもり。
Category: 未分類 |
『教師の言葉でクラスづくり 子どもにしみこむいいお話』 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月3日
桜は花びらが散っているのは
自然と散ったもので、
花ごとおちているのは、取りがつばんだものだ。
ということを、初めて知った。
すると、歩いていて、花びらの落ちているものを
ただ「ピンクの絨毯」などと喜んでいるだけでなく
細かく見てしまう。
確かに、花びらだけと花ごととの
二通りのものがある。
ピンクの絨毯に取りの存在を思うようになった。
何ごとでもそうだが、
人は知識を広げていくことで
ものの見方が変わるということだ。
学ぶことの意味は、そういうところにもある。
Category: 未分類 |
桜の花びら はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月1日
今年も、仙台親塾を実施する。
『学校と一緒に安心して子どもを育てる本』の出版に関連して
子どもを学年別に見ていくこと。
受け止めるてだて。
教師のタイプ別に応じたつきあい方。
等について、じっくりと語る。
申し込みは下記から。
http://kokucheese.com/event/index/388812/
Category: 親塾, 講座・研究会の案内 |
1 Comment »
タグ:
Posted By taga on 2016年3月30日
年度末はフェイスブックはあまり読みたくない。
卒業の投稿が多くて
その瞬間に立ち会えない寂しさやジェラシーが、ちょっとよぎるからだ。
それと、最近やたらと
「サプライズ、サプライズ」
というのが、どうも引っかかる。
六年生や中三ならば、
そこから巣立っていくという大きな節目だから
感動的な別れを子どもが演出することも
大切だと思う。
でも、低学年や中学年で「サプライズ」というのが
なんか流行みたいでいやだなあ。
それよりも、先生たちが
「サプライズでびっくりしました。」
「思いかけないサプライズ」
とか書いているのを見ると、
「この先生、大丈夫なのかなあ」
と、心配する。
だって、本当に子どもたちのサプライズ企画に全く気がついていないのならば、
いじめだって、陰で進行していたらわからないってことでしょ。
先生が子どもたちの動向に気づけないってことでしょ。
心配だなあ。
Category: 未分類 |
ほんとにサプライズなの? はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年3月27日
先日あるセミナーの後の懇親会で、若い女の先生からたずねられました。
「私は、今、二年目なんですが、どうも子どもになめられてしまうんです。なんとかしようとがんばっているんですが、どうしたらいいですか?」
僕はこう答えました。
「申し訳ないけれども、その答えを僕は持っていません。いや、僕だけではなく、今日のセミナーのどの先生に聞いても、その答えは得られないでしょう。あなたの問いに対する答えは、男性教師ではなくて、普通のベテランの女性教師が持っているんですよ。あなたの学校や周りで、怒鳴りつけずに子どもたちとうまくやっている女の先生だけが、あなたの問いに答えられます。」
地方で講演をしたとき、その後で小柄な若い女の先生が、
「私は悔しいんです。子どもをちゃんとさせられないと先輩に言われます。教師に向いていないとまで言われました。なんとかがんばりたいのです。」
と言うのを聞きました。
同じような悩みを、若手の女性教師たちは大なり小なり持っているようです。
そう。僕はその若い女性教師たちに示す答えを持ってはいないのです。なんだかんだ言っても、僕は、めったにやらなかったけれども、ここと言うときには大声を出してきました。それによって子どもたちがびしっと一瞬することは事実です。
はっきり言いましょう。男性教師の多くは、その武器を最大限に活かしているのです。子どもたちと縦糸を作るときに、その武器はかなり有効です。
しかし、女性教師がそれを背景にしようとしたら、とても難しいものです。こういうことを書くと
「男女を差別するのか」
と言われるかも知れませんが、これは学校現場での事実なのです。
いくつもの学校に指導に入っていて、ときどきすごい教師に出逢います。ベテランの女性教師で、実にうまく子どもたちを動かしていくのです。
ある小学校で授業を観ていたときのことですが、研究主任がその授業のビデオを「参観できなかった先生たちにどうしても見ていただきたいんだ」と、見せました。それは体育の準備運動の部分でした。実にスムースに子どもたちが体を動かす。しかも、先生も子どもたちも楽しそうで、充分な運動量も確保できていました。すばらしい指導でした。体育会系のびしっとした教師ではなく、やわらかい関西のおばちゃん先生でした。
現場には優れた女性教師がたくさんいらっしゃいます。
しかし、セミナーをしたり、学級づくりの著書を出したりするのはほとんど男性教諭ばかりです。現場における女性教師の比率から考えて、あまりにも少なすぎるのです。そして、女性教師の持つマニュアルこそが、最初に述べた先生方の思いに応えられるのではないでしょうか。
ずうっとそういう思いを抱いていました。あるとき、北海道の宇野弘恵先生とやりとりをしていたときに、
「ベテランの女性小学校教師の話を聞きたい若い女の先生はたくさんいるんだよ。」
と言ったら、
「実は、ずっとそういうお話をしたいと思っていました。教員の半数以上が女性であるにも関わらず、女性の書籍も講師もあまりない状況です。・・・女性はやはり下に見られ信用してもらえません。何か一石を投じたいとずっと考えていました。」
という言葉をいただきました。
それなら、僕のできることをしてみましょうと、ときどき雑誌で仕事をお願いして精度の高い実践を示して下さる藤木美智代先生に声を掛けさせていただきました。藤木先生も宇野先生と同じ考えを持っていらっしゃって、意気投合。ここで女性教師の教育論的なものができないかという方向へ向かい始めました。
その話を学事出版の加藤愛さんにしたら、
「ぜひ、本にしましょう。」
とのって下さったので、話は一気に進みました。
この本の主役は、僕ではありません。お二人の優れた女性教師です。女性だからこそ悩んできたこと、逆にできたこと。女性教師として子どもたちにどうしていくのがということ。一つの答えがこの本には詰まっています。
女性教師だけではなく、男性教師もぜひ読んでいただきたい本です。どなったり体罰したりできない時代において、女性教師のマニュアルは、全ての教師にとって意味のあるものだと確信しています。
Category: 未分類 |
女性教師論 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年3月25日
http://www.shogakukan.co.jp/books/09840169
小学館のホームページ。
アマゾンなどのネットよりも書店で売れているというのは、
なんだかうれしい。
本屋さんで手にとって買って下さるというのは、
本質だよね、書籍の。
そういう人たちがいらっしゃると思うだけで
うれしく楽しいものである。
「あとがき」から
子育てで不安を感じるおうちの方は、とても多いです。この本は、そういうみなさんに、子どもを学校に行かせるとき、少しでも安心して頂くための本です。
学校や先生にできることとできないことをはっきりさせて、その上で、家庭でもできることを具体的にまとめたつもりです。
情報の飛び交う時代です。ネットや本に示されていることの、本当に何が正しいのかが分からないようになっています。事実と突き合わせながら考えていかなければならないのですが、保護者のみなさんには、そんな余裕はありません。
そして、みなさん、子育ての経験がないのです。子育ては子どもができてからしか体験できません。兄弟がいたら、少しは二人目からは経験者ですが、兄弟そのものが第2章で語ったように全く違うものなのですから、全く同じようにはできません。
マスコミで流される事件への学校の対応の仕方を見ていると、不安が増します。
「うちの子の通う学校は、どうなんだろうか? 」と。
先輩ママたちの話を聞いていると、なかなか「すばらしい先生がたくさんいる」とは思えません。
ある程度満足している方々は、声高に語らないものです。気に入らない方の声が、どうしても大きく聞こえてきてしまうのです。それも、正しいとは限らないということです。
先生に過剰な期待はしてはいけませんが、お願いして一緒に手伝ってもらえることなら、山ほどあります。先生たちもそういうことを、本当は求めているのです。そのための手立てをいくつか示せたのではないかと思っています。
この本を書き始めてしばらくしたとき、小学館で編集に携わってくださっている福原さんに、原稿の一部を送って読んでもらいました。すると、ぼくの書きぶりに対して、どこか保護者が責任を感じたりプレッシャーを受けたりするところがあるとの指摘をくださいました。これは福原さん自身が子育てをしているからこその言葉でした。
「なるほど。そうか、この本はおうちの方々を励ます本だったね。」
そこで改めて、ぼくの中で執筆のコンセプトがはっきりとしました。おうちの方の不安を少しでも解消したい、学校への不信がちょっとでも弱まるように・・・、そう思って筆が進みました。「親塾」でずっと語ってきたこと、日ごろから考えていることをそのまま書くだけでした。240ページが、実質1か月半で書けました。それぐらい強い思いと勢いで書けたということです。
この本は福原さんの編集者であり子育てママである思いと、教師と保護者の両側に足を置くぼくの思いとが融合して生まれたものです。この本を読んで、子育ての不安が少しでもなくなってくだされば、それが本望です。
子を思うゆえに、我あり
2016年 冬
多賀 一郎
Category: 本のあるくらし, 本の話 |
学校と一緒に安心して子どもを育てる本 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年3月24日
那須まさのぶ先生と久しぶりに話した。
ダンディで、僕のあこがれる先生。
「多賀さんのやり方は、
型にはまってない。
いくつか僕の考えとは違うぞと思わされることもあるけど、
どこかの組織でがんじがらめになないから、いいんだよなあ。
日本作文の会も、昔はいろんな考えの人たちがいたけど、
組織って、どうしても一つの考え方になっていこうとするんだよ。
あなたの考え方は、それがなくて、自由だから、いいんだ。」
そう言って頂いた。
過分なお言葉であるが、
これをここにアップするのには、理由がある。
自慢話がしたいからではなく、
組織というものについてのご示唆が興味深かったからだ。
組織になると、どうしても特定の考え方に偏っていく。
そうしないと、組織が守れないところがある。
そして、その特定のやり方以外のものを否定し、排除しようとする。
その段階で、目的が組織を維持することに移る。
那須先生は、それをおっしゃっている。
日作の中枢に長年いらっしゃった方のお言葉だけに、意義深い。
いくつかの組織、グループが、まさしくそういう姿を見せている。
哀しい姿である。
Category: 社会問題・教育問題 |
組織防衛 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年3月23日
ベルギーのブリュッセルでの
爆破テロの後、
ネットでは、ブリュッセルにある金の小便小僧が
トカレフ銃におしっこをかけるという画像が
たくさん出回っている。
これは伝説が元になっている。
戦争におしっこをかけて
止めさせたぼうやの伝説。
それを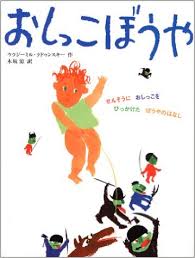
銅像にしたのが、ブリュッセルの小便小僧。
あの像は、平和を祈念した像なのである。
それが絵本になっている。
『おしっこぼうや』 ウラジミール・ラドヴィンスキー
子どもたちが笑いながら
シンプルに平和を考える絵本。
Category: 未分類 |
『おしっこぼうや』 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年3月22日
講演をほいほいと引き受けて
常に「一期一会」だと
そのときそのときの講座に集中して
作ってきた。
でも、同じところに何度もうかがうようになると、
同じ話が重なる怖れも出てきた。
きちんと自分の話は、いつどこでどんな内容だったかを
確認しなければならない。
こういうのが苦手なんだよなあ、僕は。
いつ見ても同じ話しかしないなんて、
プライドが許さない。
ということで、整理してるんだけど、
合わないなあ、僕には。
今年は、いろいろと新しい試みに取り組めるから
そういう意味では楽である。
Category: 未分類 |
整理整頓 はコメントを受け付けていません
タグ: