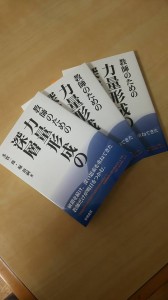Posted By taga on 2016年4月27日
人は、目に見える障害には親切だ。
白い杖をついた方に
「前見て歩け」
と怒鳴る人はいない。
車椅子の人がいたら、
周りから必ず手助けが来る。
人は本質的な優しさを持っているものだ。
しかし、発達障碍は定型発達の人から見て理解しにくい。
ただのわがままにしか見えないのだ。
人の優しさは出しにくい。
◎ 避難所の声がうるさくて、そこにはいられない。
「そんなの当たり前だ。みんながまんしてるんだぞ。」
◎ 長い時間並んで配給が受け取りにくい。
「みんな黙って並んでいるんだ。順番を待て。」
◎ ストレスを感じすぎて大声を出す。
「うるさい。迷惑だ。出ていけ。」
・・・誰だって苦しいんだ。お前たちだけじゃないんだぞ。
という考えは、まちがいではない。
しかし、いつだって障害のある人を苦しめるのは、
「みんな平等に」という言葉の持つ暴力性なのだ。
こういう方たちが悪いのではない。
理解がない。知識がない。
そのことが問題なのだ。
それが、発達障碍の人たちには塗炭の苦しみだということが分からない。
だから、ひっそりと車の中にいらっしゃる方もおられるだろう。
哀しいことだ。
僕は阪神大震災のときには、全く知識がなかったから、
そういう方々の思いへ心は向けられなかった。
知識がないと、どんな人間でも悪魔のようなことをしてしまう。
インクルーシブ教育が本当に定着したら、
このようなことで必要以上に苦しむことはなくなる。
理解が当たり前になること。
それがインクルーシブだということだ。
まず、知ることから。
Category: 社会問題・教育問題 |
災害時の発達障碍者の苦難 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月24日
またまた、言いたい放題の本を
出してしまった。
自画自賛の本。
僕と堀裕嗣の二人でないと、ここまでは書かないだろう。
書けないだろう。
著者が読み返してこんなに面白いと思う本はめったにない。
書く年代別の力量形成の在り方を
二人でそれぞれ書いている。
自分の年代から読み始めても良いだろう。
前書きを少し。
はじめに
堀裕嗣×多賀一郎の『深層シリーズ』第三弾です。
今回が一番すらすらと書けたような気がします。それは、僕らがこういう形の本の作り方に習熟してきたことと、今回のテーマが語りやすいものであったということなのでしょう。
いやあ、面白い本ができたと自画自賛したい出来ですよ。
「教師の力量形成」という言葉はよく使われる言葉ですが、「力量」とは何のことでしょうか。いろいろとご意見はあるでしょうが、僕は山を築いていくようなものだと思っています。
教師は、若い頃はいろいろな先輩方を目標として切磋琢磨します、目標とする教師に追いつきたい、あわよくば追い越したいと願いながら。 しかし、そうやって実践をある程度積み重ねてきたときに、ふと立ち止まって、自分の足跡を振り返って気づくのです、
「ああ、自分は、自分の山を築いてきたのだなあ」
と。
教師はひとりひとりが自分の山を築いていくのです。ある教師は学級づくりを中心とし、ある教師は一つの教科で自分のスタイルを確立し、ある教師は特別活動の実践家として名をはせ・・・。みんな自分だけの山を築いていくのです。その山の大きさが「力量」だと思います。大きさも質も全て違っている自分に合った自分だけの山です。
この本では、20代、30代、40代、50代、それぞれにおける力量形成の在り方について、堀さんと僕がそれぞれまとめています。堀さんは、これから50代に入っていくわけですから、未知の世界について語るということになります。
この中で我々の語っていることには、その世代の先生方にとって耳の痛い話もたくさんあると思います。別にご意見番として上からものを言うつもりは全くありません。
僕の場合は自分の経験と回りの先生達の生き方を見つめてきた総括として書いています。
堀さんの場合は、あの鋭い眼力で気持ちよくズバッと言い放っているという感じですね。(笑)
それぞれの世代別に二人の書いたことを読み比べても面白いし、僕、堀さんそれぞれの考えの流れを20代~50代にかけて読み通すと、また違った読みとり方ができると思います。
僕自身は、激動の50代をぜひとも読んでいただきたいと思っています。
続いて、「読書術」と「手帖術」というジャンルで書いています。同じようなタイトルで堀さんが編集した『THE教師力』シリーズ(明治図書)の本があり、二人とも小稿を寄せていますが、それとは全く違った視点、「教師の力量形成につながる」という視点で今回は書いています。
読書の質が大切だと言うことが、二人の話から読み取れることでしょう。
一読して全て分かってしまうような教育書は教育書に値しないと思いますし、教育書だけしか読まなければ力量形成の読書にはならないとも考えています。
僕も堀さんも読書を通じて自分を広げてきたし、結局、その部分において話のできることが、二人がこのような本を出し続けることの出来る源になっているように思います。
また、手帖術として、どうして僕らが速いサイクルで著書を書き続けることができるのか(とは言うものの、最近の堀さんのペースにはついていけないですが・・・笑)ということも、示せたのではないかなと思っています。
僕らは『深層シリーズ』を通して、もっともっと歯に衣着せぬ物言いをしていこうと思っています。そして、それに対して、さらなる議論を僕たちに返してくださることを切に願います。
2016年 春
多賀 一郎
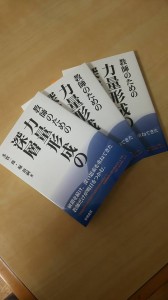
Category: 本のあるくらし, 本の話 |
『教師のための力量形成の深層』 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月21日
今日は初めて学校を休んだ。
これまで、遠くへ行くためにお願いして特別に休みを頂いたり、
家内を病院へ連れて行くという理由で休んだことはあった。
でも、自分の体調を崩して休んだのは初めて。
熱と咳がおさまらなかったので、やむを得ず。
いわゆる風邪。
だめだね、体調を崩すと。
この四年間は一度も崩さなかった体調。
今年はスタートから無理していたから、
ほっと余裕が出来たときにバタリ。
五月からの連戦に向けて
体調をもどさなければいけない。
身体が資本だね。
Category: 未分類 |
ダウン はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月17日
熊本を中心とした地震の報道に
心が潰れる。
だから、SNSでの書き込みは控えてきた。
阪神大震災のときと似ているから、
本当に辛いだろうなあと感じる。
僕が、辛いや大変だを連発してもなんの意味もない。
ただ、
頑張りすぎないでほしい。
人のため、アドレナリンが出て、
ハイテンションになり、
頑張りすぎてしまう。
それで、時間が経ったときに、心が空っぽになる。
そこからは、かなり苦しい状態になることがある。
立派になりすぎないでほしい。
泣いたりわめいたり、
わがまま言ったりして、吐き出してほしい。
やりすぎないことを、今、地元で人のために懸命に動く方達に願う。
Category: 震災について |
祈り はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月14日
恒例の6~7月にかけての
東北ツアー。
震災の復興支援のつもりもあり、
数日間の東北滞在。
今年は、気仙沼へ行く。
昨年の秋にお約束して、実現することになった。
6月28日に気仙沼。
でも、気仙沼って遠いんだよね。
次の日に仙台へもどり、30日の木曜の午前中に親塾。
7月1日に石巻の学校へ行き、
2日は石巻セミナー。
これも2回目だ。
今年は少し旅感覚で行こう。
Category: 未分類 |
気仙沼、決まり はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月12日
この時代、
準備せずに新年度に臨むのは危険である。
しかし、若い先生は準備すると、
どうしても全部したくなってしまう。
それも、短期間に。
これまた危ない。
例えば、僕が若手によく言うのは、
学級のルールをたくさん作るなということ。
学級をこうしたいということをいくつもあげていって、
書き出すまではいい。
でも、それを全部スタートからの指導項目にしてはいけない。
10項目も「学級のルール」をはりだされたら
息苦しくっていけない。
しかも、そういうことを提示する教師は、「学習のルール」も10項目だったりする。
少しずつ、余裕を持ってスタートしていくこと。
一気に全部なんとかしようなんて、
神業を持つ特殊な教師にしかできない。
美味しい肉であっても、10キロも食べたら身体を壊す。
身体に良いからと言って、毎日ヨーグルトを1キロ飲むなんてできない。
教師は気づかずにそういうことを子どもに強いてしまうときがある。
やらなければならないことは、3つか4つに絞り込んで
それを徹底していくことが大事だと思う。
あわてずに、粛々と準備したことをていねいにしていく。
絞り込んだものを徹底して、それのできる状態にしていくことが
今の時期に必要なことではないか。
Category: 教師へのメッセージ |
消化不良に注意 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月11日
新人に最初にアドバイスしたことは
「ともかく、子どものそばにいなさい。
子どもと遊びなさい。
何を放っておいても、休み時間は子どもたちと遊びなさい。
最初が大事なんですよ。最初から遊んでいると、
子ども達は
『この先生は自分たちと遊んでくれる先生だ』
という印象を持ちます。
凄い技術のあるはずがないんだから、
せめて、子ども達と一緒にいましょうよ。
一緒に遊んで共に笑っていたら
『仕方ないなあ、いうこと聞いてあげよっか。』
ということになるものですよ。」
ということである。
月曜の業間。
ベランダから運動場の様子を見る。
新人は全員、子ども達と走り回っていた。
子ども達と先生の笑顔がはじけている。
まず第一歩は、合格かな。
この先、困難や苦しみもあることだろうが、
教師はこの笑顔が大切なんだよ。
Category: 教師へのメッセージ |
遊べ、遊べ はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月10日
今日は一日、のんびりした。
昨日の、
120分の学級づくり、
80分の発問づくり、
30分の発問のサイドメニュー、
70分の本と国語の教育、
さすがに、疲れたが
心地よい疲れ。
やり切った感が強いから。
後の二度付け禁止の串カツにもほっとした。
今日は家内が犬の散歩まで行ってくれて、
少しのんびりした。
で、秦建日子の『殺人初心者』を読み切り、
いくつかの講座づくりと資料の印刷。
ゆったりした時間。
徐々に頭と身体を回復させていく。
こういう時間が必要なんだなあと思う。
Category: 未分類 |
ゆっくりした はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月8日
水曜日、守口市の小学校で2時間半お時間を頂いて
新年度に向けての「聴く」講座をした。
最後に、30分、絵本を読んだ。
絵本を読み聞かせする先生が増えるといいなあ。
3日の「教師塾」に来ていた若手たちは、
さすがに僕のところへ来るだけあって、
みんな絵本を教室で読み聞かせする。
僕も一つだけ、
『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』
の読み方を指南した。
僕の部屋の絵本を取り出して写メ撮って、
おそらく購入して教室に持っていくのだろう。
「何年生には、この絵本がいいよ。」
「こういう授業開きには、○○の絵本だよ。」
こんな会話も自宅での「教師塾」ならではのこと。
絵本には力がある。
塾生たちは、そのことを強く認識している。
Category: 本の話, 絵本の話 |
絵本の力 はコメントを受け付けていません
タグ:
Posted By taga on 2016年4月7日
追手門は、アクティブ・ラーニングへの舵を切った。
どう考えても、私立小学校はこのことと向かい合わないといけない。
昨年度から少しずつその話をしてきたが、
大きく動き出す。
世間の風潮にのるわけでもなく、
文科省に引っぱられるわけでもなく、
追手門の子どもたちを見つめながら、
これからの追手門の子どもたちに必要なものを創っていくということだ。
僕も、授業をする。
1時間の投げ込みだけでは何も伝えられない。
5時間ぶっ通しで教科書教材を使ってのアクティブ・ラーニング。
大切なことは、いろいろと試みながら考えていくことだ。
答えは誰も持っていないのだから。
文科省教育課程課長の合田氏も
「『アクティブ・ラーニング、これをすれば絶対大丈夫』
『アクティブ・ラーニング、これ以外にはない』という『型』にとらわれて授業をすることは
むしろ主体的・対話的な深い学び(アクティブ・ラーニング)の対極で、
このような特定の型を表面的に整える指導は、パッシブ(受けて)・ラーナーによる授業の典型と言えよう。」
(『教育研究』2016年4月号)
と言っているように、
巷にあふれる「われこそはアクティブ・ラーニング」的なことに惑わされず、
子どもたちの姿、学校や地域の特色を踏まえて
少しずつ、まずはやってみることが大切なのだと考えている。
Category: 社会問題・教育問題 |
アクティブ・ラーニングへのスタート はコメントを受け付けていません
タグ: